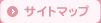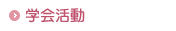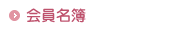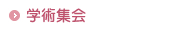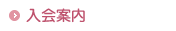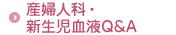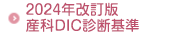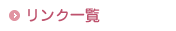日本産婦人科・新生児血液学会
事務局
産業医科大学
小児科学教室内
〒807-8555
北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1
TEL. 093-691-7254(直通)
FAX. 093-691-9338
学会の概説
日本産婦人科・新生児血液学会の設立とその後の発展 — 20年を振返る —
浜松医科大学名誉教授 寺尾俊彦
学会の第1回学術集会(会長:浜松医科大学産婦人科寺尾俊彦教授)が,平成3年(1991年)6月,浜松市で開催された。それから20年が経ち,平成22年(2010年)6月,第20回学術集会(会長:浜松医療センター小林隆夫院長)が,再度,浜松市で開催された。
本学会が誕生するまでの経緯は,周産期医学(日本産婦人科・新生児血液学会の誕生. 1992; 22(4): 449-50.)において既に述べているので,ここにその一部を抜粋しながら,往時を振返ってみたい。 その後20年の間に血液学は著しく進歩した。産婦人科や新生児の領域における血液学分野も、連動して同様に大きく進歩した。 このうち、最初の10年間の進歩については,周産期医学(周産期医療における血液をめぐる問題. 2003; 33(2): 145-53.)において概説しているので,その一部をここに抜粋しながら振返ってみたい。 最近10年の進歩も著しい。この詳細については稿を新たにしなければならないが、この10年間には,学会主導の重要な共同研究が行われ、本学会にとっても大きな進展が見られた。このように本学会が設立された意義は極めて大きい。この20年間に本学会の発展に寄与された役員や会員の皆様に深甚なる謝意を表したい。 (1)日本産婦人科・新生児血液学会の誕生
血液を知らずして産婦人科医たり得ない。このことは子宮が人体の中で唯一の生理的に出血する器官であり,産婦人科医が月経や分娩時出血の管理を職とすることからも明らかである。日本の産婦人科医は古くから分娩時異常出血に対する関心があり,医療レベルも世界的にみて高いものであった。現在では医師なら誰でも知っている血管内血液凝固(DIC)という概念に関しても既に古くから普及していた。 DICの発生機序を実験的に初めて証明したのは日本の産科医,小畑維清氏である。また臨床的には戦後,進駐軍の米軍軍医として来日したSchneider氏によって紹介され, intravascular clotting ,産科的低線維素原血症,消費性凝固障害などの名のもとに日本の産科医の間には広く浸透していた。 その他の分野でも血液学の関心は高く,妊婦貧血,母児間血液型不適合妊娠,メレナ,血液疾患合併妊娠などが主な研究対象であった。年々,研究者の数も増加し, 同好の士が集って昭和51年に第1回産婦人科血液研究会が開催された。この開催には品川信良,相馬広明,鈴木正彦,真木正博の諸氏らが尽力され,エーザイ(株)の協賛を得て,東京で開かれた。以後,毎年1回開催され,更に昭和56年,第6回からは小児科に関連する分野も含めた産婦人科・新生児血液研究会となり,その規模もいっそう大きなものとなった。 平成2年6月には山田兼雄会長のもとで第15回研究会が開催されたが, これを記念して「産婦人科血液ハンドブック」(医学図書出版㈱)が刊行された。この研究会の学会誌ともいうべき「産婦人科・新生児血液」は昭和52年の初刊から第14巻第1号まで刊行され, この出版には医学図書出版(株)の鈴木社長の多大な御協力をいただいた。そこでそれに感謝して原稿料無料の奉仕で会員が執筆し,「産婦人科血液ハンドブック」が上梓された。また,これを機に研究会を学会に昇格してはどうかという声があがり,早速,設立準備委員会が発足した。 そして第1回の学会を小生がお世話することになった。時間的制約もあって取りあえず旧研究会のメンバーを中心として会則をつくり,役員も過渡的措置として旧研究会のメンバーで構成した。 第1回の学術集会を平成3年6月20日〜21日,浜松名鉄ホテルで開催された。特別講演(高田明和教授, 線溶系研究の最新の進歩),シンポジウム2題(未熟児管理と血液学的諸問題,組織の接着・修復と血液に関する進歩),及びワークショップ12項目(妊娠と血液凝固線溶,血液凝固異常とその管理,生殖と血液,新生児と血液,周産期と血小板減少症,習慣流産と血液凝固,血液型不適合妊娠,最適な輸血,HTLV-1感染,脂質代謝と血液,妊娠と水分代謝,悪性腫瘍と血液)が発表され,熱心な討議が行われた。 学会誌は年4回発行されることになった。表紙には「母と子の血液が繋がっていること」を表すロゴマークを掲載することにした。また、ISSN番号を取得して逐次刊行物として国立国会図書館に収めることにした。 学会が設立された当時から既に、血液学の進歩は著しく,血液学が単に血液だけにとどまらず,あらゆる医学の分野に深く関連することが明らかになって来ていた。それに伴い研究者数も学会発表や業績の数も年々増加していた。産婦人科や新生児の領域でも例外ではない。血液学の進歩はその裾野を広げたばかりか,一方では細分化し,より専門的な知識を必要とする時代に入った。このような状況を背景として,会員相互の情報交換の場が必要であるとの気運が生れたといえよう。 MDとPhDを含め世界で最も研究者数が多いのは血液に関する分野であり,従ってその進歩はとどまるところを知らない。 例えば血液凝固因子に関する研究について考えてみると,従来,血液凝固線溶のカスケードは蛋白の分画と活性の性質や特異性を指標として数十年もかけて明らかにされて来たが,本学会が設立された頃には,そのアミノ酸配列からDNA配列まですべて明らかとなり,リコンビナント製品まで製造されるまでになった。凝固線溶因子が相互に作用しながらホメオスターシスをバランスよく保っている機構も明らかにされた。また、血液凝固因子は止血のための因子であると同時に組織の接着,修復,血管の再生,成長,細胞増殖にも深く関与していることがわかった。したがって,着床や妊娠維持のための胎盤と子宮の接着,すなわち生殖現象や妊娠の維持機構に必須の物質であることが明らかにされた。更にまた,血液凝固線溶系の物質が癌の浸潤や増殖に必須なことも明白となった。癌細胞はウロキナーゼを分泌し,癌細胞表面にあるウロキナーゼ・レセプターと結合し,autocrine,またはparacrineタイプの分泌をすることによって細胞外マトリツクスを分解し癌細胞自身が浸潤して行くとともに,細胞増殖にも関与していることも明らかにされた。このように血液凝固因子に関する研究も血液学の分野から生殖医学,腫瘍学の分野にまで,裾野を拡げるに至った。 産婦人科新生児領域における血液学は他科領域のそれとは違うので,産婦人科医や新生児を取り扱う小児科医自身が研究の当事者である必要がある。妊娠,分娩,産褥という特殊な状態,胎児,新生児という特異的な状態での血液学は他科領域の研究者が行うことは不可能である。
このようなことを背景に学会設立の気運が生まれたのであろう。 (2) 学会設立後の進歩
「周産期と血液」と言えば,「産科出血」を連想する程,古来,産科医にとって出血は最重要課題であった。幸いなことに,医学の進歩や医療態勢の改善に加え,社会の理解も深まったこともあり,出血による死亡は激減してきた。しかし一方では,出血による妊産婦死亡が医療訴訟へと向かうようになった。周座期医療に従事する者には,出血管理に関する高度な知識や技術が求められている。 一方、「血栓」の問題が重要課題として登場した。近年,高齢化や食生活の欧米化により,脳梗塞,心筋梗塞,肺塞栓症,深部静脈血栓症などの血栓性疾患が増加している。ことに問題となっているのは,術後,あるいは分娩後の致命的な肺塞栓症である。帝王切開術後の産褥期に致命的な肺塞栓症が起こると,誕生の喜びが母体死亡の悲しみへと事態は一変する。出産の高齢化,帝王切開頻度の増加,食生活の欧米化などの後天性血栓症素因のリスク・ファクターが影響していると思われる。 また,薬剤投与による血栓症の発生も問題となっていた。ダナゾールによる脳血栓,hMG-hCG製剤(卵巣過剰刺激症候群)による脳血栓が新聞紙上で大きく報道された。第三世代の低用量経口避妊薬が第二世代のそれよりも血栓症が発生しやすいとの報告も世界を駆けめぐった。また,ホルモン補充療法の安全性に関する大規模調査でも,ホルモン投与により血管性病変はやや増加すると報告された。 血液疾患合併妊娠も実地医家にとっては重要な問題である。医学の進歩とともに,その対応の仕方も変わってきている。例えば急性前骨髄球性白血病に対しATRA(all-trans-retinoic acid)併用化学療法が行われ寛解が得られ,一方また,化学療法が妊娠中に行われたケースでの児の長期予後も報告されるようになっている。血液疾患合併妊娠の取り扱いに変革がおきている。 貧血も古くて新しい問題である。近年,貧血の頻度が増加している。香川県 血液センターの報告によると,比重不足により献血できなかった女性の割合が,年々1%弱ずつ増加し, 1992年の11.5%が2001年には19.2%になったと いう。若い女性が不適切な食生活をしていることによるものと思われる。 血液凝固因子は単に出血・止血に関与しているだけではなく,細胞同士を接着する作用も担っている。これを知る手がかりが先天性血液凝固因子欠乏症と妊娠の成立との関係である。着床および子宮と胎盤との接着には血液凝固・線溶系物質が関与していることは明らかである。そのモデルとして先天性無線維素原血症と先天性XIII因子欠損症患者の妊娠があげられる。両者ではいずれも妊娠初期に出血が開始して流産してしまうが, fibrinogen,XIII因子をそれぞれ補充することによって妊娠は維持され生児を得ることができる。 このほか子宮と胎盤との接着に関与する物質としてcollagen,fibronectin,lamininなどをあげることができる。これら接着性物質と妊娠・分娩との関係も次第に明らかにされてきた。 血液凝固機構は,血液の流動性の保持と血管の破綻の修復・止血という相反する仕事を行い,ホメオスターシスを保っている。そのいずれかの機能の破綻が,「出血」,あるいは「血栓」である。 しかし,この機構は極めて巧妙で複雑であり,単に血液凝固のみならず,血管内皮・血管周囲細胞 や生理活性物質・末梢神経との相互作用で血管収縮・弛緩とも関連して,その機能を果たすことができる。この機能の破綻として 妊娠中毒症(現在の妊娠高血圧症候群),子癇,HELLP症候群などの一連の疾患が挙げられる。これらは過凝固状態を背景に発症し,血液凝固と血管の攣縮が密接な関係にあることを示している。Dekkerらは,重症の妊娠早期発症型妊娠中毒症(妊娠高血圧症)はthrombophiliaの患者に発症すると報告した。 近年,thrombophiliaという概念が生まれ,新しい血液凝固制御機構も明らかになってきた。この流れついては本学会誌に概説した(寺尾俊彦: 産婦人科とthrombophilia,日本産婦人科・新生児血液学会誌, 6巻2号 Page12-32 1996)。 (1)先天性thrombophiliaには,1)凝固因子欠乏症として,アンチトロンビンIII(ATIII)欠損症,ヘパリンコファクターII(HCII)欠損症,プロテインC欠損症,プロテインS欠損症,トロンボモジュリン(TM)欠損症,活性化プロテインC(APC)レジスタンス,プロテインC/APC受容体(EPCR)欠損症,2)線溶系因子の異常として,プラスミノゲン欠損症,組織プラスミノゲンアクチベータ(t-PA)欠損症,プラスミノゲンアクチベータインヒビター1(PAI-1)増加症,ヒスチジンリッチグリコプロテイン増加症,3)その他の因子の異常症として,フィブリノゲン異常症,アポリポプロテインLp(a)増加症,ホモシスチン尿症などの存在やその異常に伴う病態が明らかになってきた。一方、(2)後天性thrombophiliaは,非家族性の要因により易血栓傾向をきたす疾患をいう。抗リン脂質抗体症候群,悪性腫瘍,妊娠,経口避妊薬服用,溶血性貧血(鎌状赤血球症,サラセミアなど),肥満(体重指数>30 kg/m2),静脈瘤,加齢(年齢40歳以上),手術後,寝たきりなどの不動の状態,外傷後,脱水症,濃縮凝固製剤輸注,高血圧症,高脂血症,重症感染症,糖尿病など,種々の原因により血栓症をきたす。これらはいずれも深部静脈血栓症・肺動脈血栓症(肺塞栓症)のリスク・ファクターである。 抗リン脂質抗体症候群(antiphospholipid antibody syndrome)とは,その患者の血中にミトコンドリア内膜由来のカルジオリピンや細胞膜を構成するホスファチジルセリンなどのリン脂質およびこれに結合した蛋白に対する自己抗体,いわゆる抗リン脂質抗体を有する疾患群の総称である。血栓症,習慣流産,血小板減少症などの臨床症状に加えて抗カルジオリピン抗体(anticardiolipin antibody:aCL)や,ループスアンチコアグラント(1upus anticoagulant : LAC)が証明されると本症と診断される。抗リン脂質抗体はカルジオリピンなどの陰性荷電を有するリン脂質に対する抗体と考えられていたが,分子生物学的研究により抗リン脂質抗体の対応抗原はリン脂質そのものではなく,β2-glycoprotein l (β2GPI)やプロトロンビン,プロテインC,プロテインSなどの各種血漿蛋白やアネキシンVなどの細胞質蛋白であることがわかった。すなわち、抗リン脂質抗体とはβ2-glycoprotein 1 (β2GPI)やプロトロンビンが細胞膜上に露出した陰性荷電を有する脂質に結合することにより構造変化をきたし,新しいエピトープが出現,この新しい結合物を認識する抗体,言い換えるとリン脂質・蛋白結合物質を認識する免疫グロブリンであることがわかってきた。そこで最近では抗リン脂質抗体という表現は適切ではなく,リン脂質結合性抗血漿蛋白抗体と表現される概念に変わりつつある。 また、血管内皮細胞には種々の抗血栓機構が存在し,血液の流動性を保持している。血管内皮細胞上の凝固制御機構としては, 1)thrombinの生成を阻害する機構としてprotein C 凝固制御系,2)線溶を制御する機構としてthrombin acivatable fibrinolysis inhibitor(TAFI)系,そのほかに,3)thrombinを直接阻害する機構としてantithrombin凝固制御系,4)prostacyclinによる血小板凝集阻害系などがある。 antithrombin凝固制御系においては,内皮細胞上のヘパラン硫酸プロテオグリカンがthrombinおよびantithrombinと結合し,両者の複合体を形成することにより血管内凝固を防止している。 プロテインCの活性化機構は,内皮細胞上のthrombomodulinが,thrombinを結合してその基質特異性を変え,フィブリン形成能や血小板活性化能を阻害するとともに,プロテアーゼ前駆体のプロテインCを活性化することにより起こる。その頃,プロテインC受容体(EPCR)が発見された。 APCがEPCRに結合すると,プロテインCがさらに活性化されやすくなる。 APCは,コフアクターのプロテインS および第V因子の存在下に凝固系の重要な補酵素であるVa因子とVIIIa因子を失活して凝固反応を阻害することにより血栓形成を防止している。
一方,thrombin activatable fibrinolysis inhibitor(TAFI)系も、同様にその頃、発見された重要な線溶制御系である。TAFIは,APCと同様thrombin-thrombomodulin複合体により活性化されるが,線溶系を制御している。凝固系はAPC,線溶系はactivated thrombin activatable fibrinolysis inhibitor(TAFIa)により制御され,この両者のバランスによりホメオスターシスが保たれている。 thrombin-thrombomodulin複合体が,効率よくプロテインCを活性化してAPCにする。一方では,thrombin-thrombomodulin複合体は,thrombin activatable fibrinolysis inhibitor(TAFI)を活性化してactivated TAFI(TAFIa)にし,TAFIaはフィブリンからcarboxy-terminal lysines を除去する。carboxy-terminal lysines はフィブリンのプラスミンによる限定分解によって表面に現れ,プラスミノゲンやtPAが有しているlysine-binding sitesに対するリガンドとして作用する部位であり,フィブリンからcarboxy-terminal lysinesが失われると線溶は起こらなくなる。TAFIの活性化はプラスミンやトリプシンでも起こる。 また,血液凝固は免疫や炎症とも密接に関連している。ヒトは進化の過程で,外傷(出血・止血) や感染(免疫)を克服する能力を獲得してきた。したがって,免疫,炎症,血栓,血管新生は,外傷や感染に際して同時的に,あるいは順次的に働き,その場合には,多種多様なサイトカインが血管内皮細胞・血管周囲細胞に働いて機能する。
学会設立の前後は,これらに働く分子の発現機構が明確にされていく黎明期にあり、その後飛躍的に発展した分野である。(詳細は前述の周産期医学2003; 33 (2): 145-53.に記したので参照されたい)。 前述のように,近年では肺塞栓症,深部静脈血栓症などの血栓性疾患が増加し、ことに術後,あるいは分娩後の致命的な肺塞栓症が問題となり、肺血栓塞栓症/深部静脈血栓症(静脈血栓塞栓症)予防ガイドラインが作成された。このガイドラインの作成には日本血栓止血学会,日本産科婦人科学会,日本産婦人科・新生児血液学会,日本集中治療医学会など多数の関連学会が参加した。本会からは作成委員として小林隆夫信州大学保健学科教授(当時)が参加して実務を行い,外部評価委員としては私が加わった。予防のための産科ガイドライン,婦人科ガイドラインが作成された。 ノボセブン®HI(活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤)の産科出血止血効果に関する共同研究も本会において開始された。ノボセブン®HIは,第Ⅶ因子欠乏症患者,後天性血友病,第Ⅷ因子または第Ⅸ因子に対する抗体(インヒビター)を有する場合を適応とする製剤であるが、欧米では大量出血時の治験が開始されている。組織因子や活性化血小板とともに、第X因子を活性化させ、血液凝固反応を進めるので大量のトロンビンが産生され、その結果、安定した血餅(フィブリン網)を作り止血効果を発揮する。極めて高価であることが難点である。 本会の開催時には、新生児・乳児ビタミンK欠乏症研究会も併せて行われてきた。この研究会は本症の啓発に極めて有意義であった。本症は,生後1か月頃に頭蓋内出血を起こして死亡する症例が多いので,ビタミンK2シロップを生後1か月までに3回,各2mg与える予防法が行われてきた。この予防法によって10万人当たりの発症率は平均18人(1978~80年)から2人(1990年)まで低下したもののゼロにはならず、生後2〜3ヶ月に発生する例を予防できていないことが分かった。そこで新しいガイドラインを作成して予防することになった。母乳栄養の場合には、3ヶ月まで毎週2mg投与することになったが、現時点で2mgに分包したシロップの製品がないので、製造承認がなされ市販されるまで待つことになった。以上のように,血液領域分野の進歩や変革は著しい。これに対応するには本会のような特化した学会が必要であり、本会の存在意義は極めて大きいと言える。